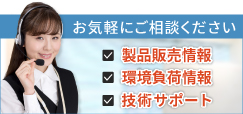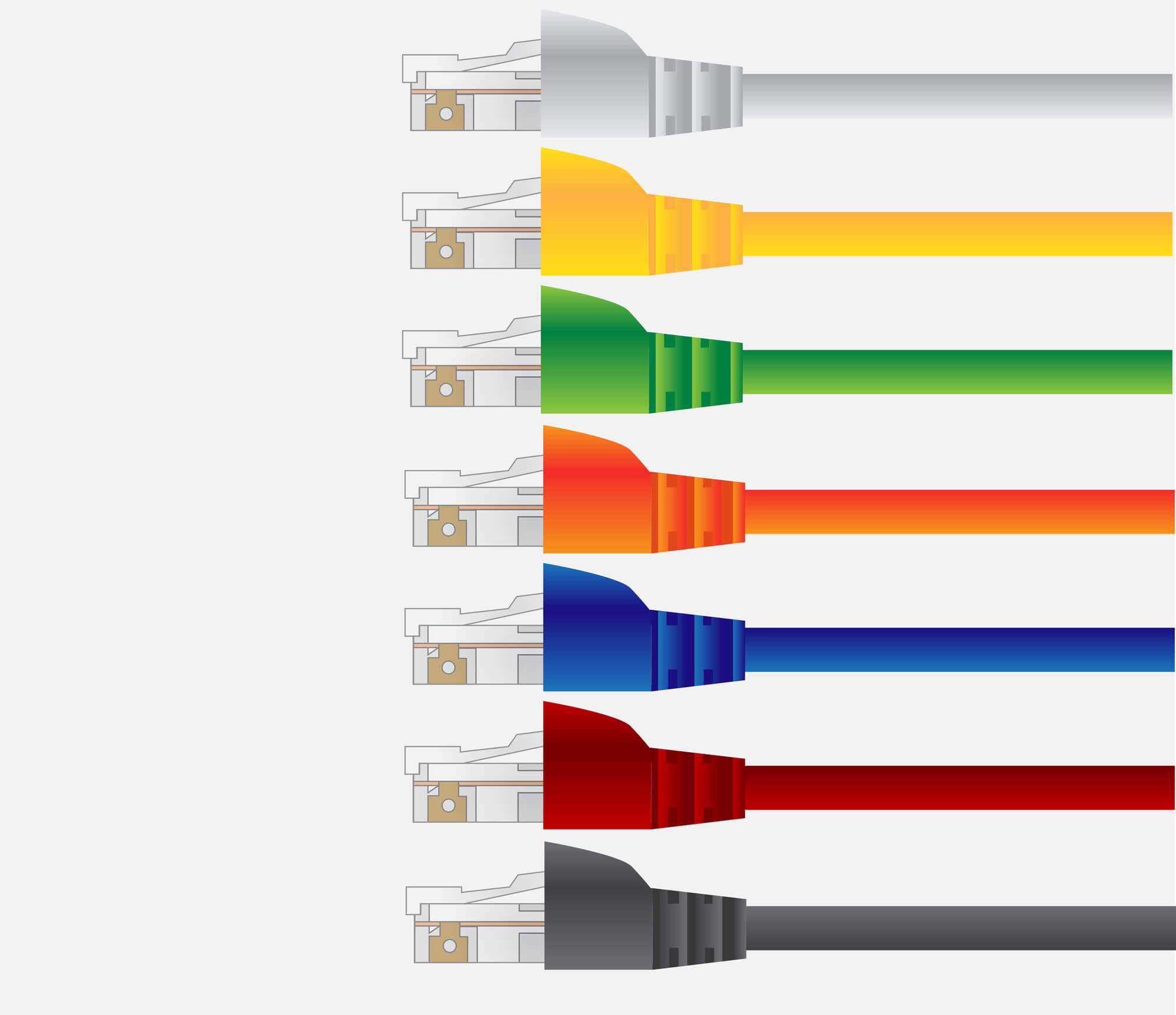ケーブルの「塩害」とは
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります

「塩害」という言葉を聞いたことはありますか。多くの方にとっては聞きなじみのない言葉かもしれませんが、海沿いの地域では警戒すべき問題の一つです。建築物や植物は塩害の悪影響を受け、ケーブルもまた塩害の対象になっています。こちらでは、塩害の概要やケーブルに起こり得る被害、一般的な塩害対策についてお話します。
塩害とは
塩害とは、塩分を含む風または海水によって引き起こされる、建築物・構造物・植物への被害の総称です。特に、海沿いの地域では塩害が多発します。また寒い地域では、雪を溶かすための融雪剤に含まれている塩化カルシウムが塩害を引き起こすこともあります。
多くの農作物は、塩分が過剰に多い環境では生息できません。また一度塩害が発生すると、数十年規模で農作物の作付けが難しくなると考えられています。津波に匹敵する被害として、農業地域に塩害が起きた例は数多く存在します。
塩害がもたらす無機物への悪影響の代表的な例として、さびや急速な劣化が挙げられます。比較的古い構造物の場合であれば、塩害によって崩落してしまう可能性もあります。海沿いを走る電車が塩害により、早期のうちに廃車になってしまうケースもあるようです。
日本では、沖縄や離島・瀬戸内海側・東北日本海側・その他の海岸から500m以内の地域が「重塩害地域」として定義されています。
ケーブルに起こりうる塩害
塩分の多い環境で屋外に露出している場合、ケーブルにも塩害が起こり得ます。塩害の対象となる代表的なケーブルは、電線や配電ケーブルです。ケーブルをまとめるプルボックスやケーブルラックに塩害が発生することもあります。
塩分は電気を通しやすく、絶縁部に塩分が付着すると漏電が起きると考えられます。最悪の場合は、電気の供給が停止してしまうこともあります。
被膜へのダメージも少なくありません。塩害によって導電体が露出した状態は大変危険のため、海沿いに設置されたケーブルには塩害対策が必要となります。
ケーブルの塩害対策
塩害が予想される地域では、電気設備に対策を実施することが前提となります。ケーブルにも耐塩性の強い被膜や塗装が施されます。また、付着した塩を定期的に除去するのが一般的です。
***
塩害対策は基本的に海沿いの地域に求められる措置ですが、潮風が台風などの影響で海から遠く離れた地域にも届くことがあります。塩害対策が施されていないケーブルは塩分に対して脆弱です。屋外にケーブルが露出している場合は、必要に応じて塩分への耐性に注目してください。